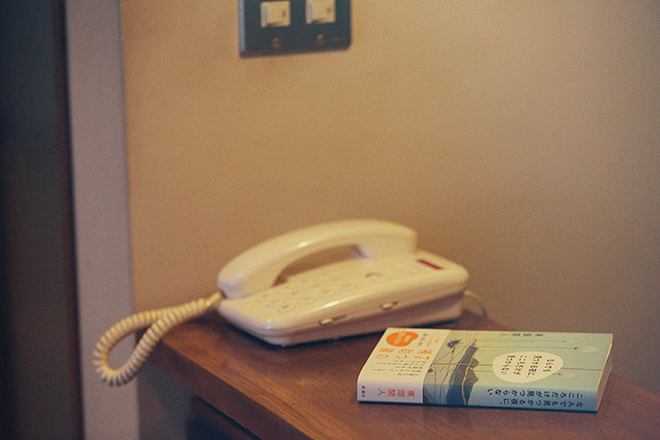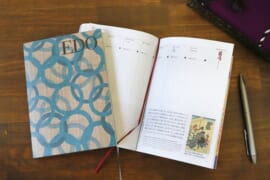心理士として15年、人々の心の問題に向き合ってきた東畑開人(とうはた・かいと)さん(39)による新刊『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』(新潮社)が3月16日に発売。1週間足らずで重版が決定し、話題を呼んでいます。
これまで私たちを守ってくれていた社会のしくみやつながりが壊れ、遭難しようが沈没しようが自己責任の“小舟化した社会”。自由だけれど気がつけば孤独に陥りやすい社会で私たちはどんなふうに生きていけばいいの?
東畑さんに3回にわたってお話を伺いました。第2回目のテーマは「モヤモヤするって悪いこと?」です。
「スッキリする」だけが悩みの解決法ではない
——「スッキリとモヤモヤ」(6章)も興味深かったです。スッキリすることで心を守るやり方と、モヤモヤすることで心を守るやり方があるという……。どちらかというと「モヤモヤ」は「心を守れなかった結果」「悪いこと」と捉えていたのでハッとしました。
東畑開人さん(以下、東畑):「苦しいからスッキリする」が主流なのは、それだけ社会が追い詰められている証拠かもしれません。でも、人の悩みは、スッキリする以外にも、解決法があるんじゃないか、と思うんです。
余裕がないときや「悪意のある人からの説教」や「嫉妬からくる忠告」などは真面目に受け取っても心が疲弊するだけなので、確かにスッキリしたほうがいいと思うけど、多少はモヤモヤできる力が宿っているときもあるじゃないですか。そのときにスッキリしちゃったら、苦い良薬を吐き捨てるようなものだと思っていて。
今は答えが複数あるがゆえの、方向喪失の時代です。明確な答えがないからこそ当然モヤモヤもする。それって自然な反応ですよね。つまり、モヤモヤの良さは、現実とちゃんと付き合うということなのではないかと思うんです。
「モヤモヤ」のトリセツ
——確かに現実や問題とちゃんと向き合っているからこそモヤモヤするのかも……。
東畑:ただ、一人でモヤモヤするのは良くないので、誰かとモヤモヤすることが大事だと思います。今の学生は、「ちゃんと悩んでキャリアを決めていきましょう」とか、結構言われているわけですよ。そうすると、学生は「よし! ちゃんと悩もう!」と思って、布団の中で悩み始めるわけです。でもそれって、同じ思考がグルグル回っているだけなんですよね。
「ちゃんと悩む」って、「現実」や「世界」に触れて、こうでもないああでもないと考えることだと思うんです。例えば、自分が就きたい仕事について考えるなら、実際にインターンに行ってみるとか。そして、一人で悩むのではなくて、誰かに話してみる、その場所に実際に行ってみる、とか。現実に触れてみると、ちゃんとモヤモヤできるのではないだろうかと考えています。
——「世界」に小石を当てて様子を見てみるようなイメージでしょうか。そういえば、先日ちょっとモヤモヤしていたときに友人にLINEで話を聞いてもらったら「どんな状況だったの?」「それでどう思ったの」とかいろいろ質問を投げかけてくれて、「あ、自分はこうしたかったんだ」と整理できました。まさに「補助線」を引いてもらったというか……。
東畑:素晴らしいですね。誰にも話せないことを話すのは治療的なことだと思います。カウンセリングも根本的には同じことをしているんです。モヤモヤって言葉にならないんですね。言葉にならないからモヤモヤするわけで。それを言葉にするために、いろいろと考えないといけないからカウンセリングというものがあるのだと思うんですよね。そういう意味で、モヤモヤを人に話すというのは素晴らしいことだと思います。
——自分が何にモヤモヤしているのか分からないこともありますもんね。
東畑:そうなんですよ。だから、今おっしゃってたみたいに相手に質問してもらうといいかもしれませんね。「何が起きたの?」って聞かれると、ちょっと何か出てくるじゃないですか。モヤモヤって言葉にならないものだし、人に話さないと分からないんだと思います。
複雑な現実をできるだけ複雑に生きること
——質問といえば、前回もお話にあった、誰かと本当につながりを結べる人やナイショの関係を築くのが得意な人というのは「質問力がある人」なのでしょうか?
東畑:質問力ではなく、希望のある人なのではないでしょうか。「そんなに悪いことは起こらないだろう」「何か良いことがあるだろう」というように、他者に対して辛抱強く希望を抱ける人。テクニックではないと思います。テクニックって、相手を信頼してないから使うものでしょう?
——確かにそうですね。「失敗したくない」「傷つきたくない」ときにテクニックを駆使しまくりますね。
東畑:ですよね(笑)。だからみんな失敗しないために会議の前にアジェンダを共有する。
——他人に対して希望を持つというのは、「他者と真剣に向き合う」ということなのでしょうか?
東畑:そうだと思います。つまり、「他者に絶望しているかもしれないけど、他者に希望を持っている自分もいる」ということですよね。
本の最後に書いた「も」の思想ですね。あなたに悪意を向けてくれる他者もいれば、あなたの苦痛に無関心な他者もいる。でも、そこには善意を抱いている他者「も」いるはずだし、あなたの苦境を見て見ぬふりできない他者「も」いるということ。複雑な現実をできるだけ複雑に生きること、それが幸福につながる道だし、大人になるということなんだと思います。
※第2回は4月14日(木)公開です。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)